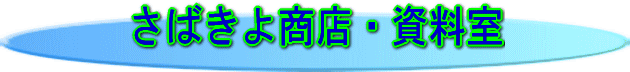
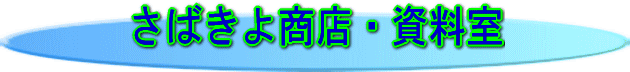
| 資料№1:自治体の最適人口 | |
| 『最適規模自治体の研究』(総合行政出版 286頁 2300円 平成4年3月発行)は「地域経営に責任の持てる自治が出来るためには人口13万人以上が必要であり、それ以下の自治体は衰退する可能性が高い」と結論づけました。また、最も経営効率(費用対効果)が良い自治体の人口は、15万人といわれており、これを下回っても、上回っても非効率となる様です。 | |
| 清瀬の人口に戻る |
| 資料№2:ナンバリング地名 | |||||||||||||||
| ナンバリング地名とは? | 地名を新たにつける時、一二三とナンバーをつける様に地名をつけていったので、ナンバリング地名と呼ばれています。清瀬では、もともと他の地名だったものが、わかりにくく改名する事になり、松竹梅と頭につけて地名を決めたと思われます。 |
||||||||||||||
| ナンバリング地名の実例 UP |
ナンバリング地名の実例として、北総台地につけられたものが、あげられます。明治維新後の新政府の課題は、東京にいる失業者や生活に困っていた武士の救済でした。そこで、下総の北総台地(松戸市、鎌ヶ谷市、柏市)などの開墾を彼らにまかせてその解決を図ろうとしました。 |
||||||||||||||
| 清瀬の地名に戻る | |||||||||||||||
| 資料№3:全国で明治22年(1989年)の町村制施行以降、他の市町村と合併をしていない都市 | |||||||||
| 現在全国には、671の都市(東京特別区を1都市として数える時は672都市)がありますが、そのうち東日本地域で明治22年(1989年)の市町村制以降、他の市町村と合併をしていない都市が、清瀬市を含め24都市ありました。以下はその一覧です。調査資料が、少し古いためもし間違いがございましたらご指摘下さい。なお、西日本地域では、8市あり、今後詳細を調査掲載予定です。 | |||||||||
| 関連事項1:市町村の合併を考える時、重要なポイントは、昭和28年9月1日公布の 町村合併促進法です。いわゆる「昭和の大合併」です。この法律に基づき、政府は人口8,000人以上をめどに、県を通じた市町村合併計画の策定、合併に消極的な市町村への総理大臣勧告など強力な指導によって合併を進めました。この結果、市町村数は約3分の1となり、昭和29年には、全国で176市が誕生しました。この時点で市制施行を終えていたり、または、標準人口などの基準を満たした町村の一部がここであげている合併が無い都市になったわけです。(標準人口8000人は、戦後、小・中学校が市町村立となり、新制中学の効率的運営に最低限必要な人口として算出され、この基準の根拠となりました。) | |||||||||
| 北海道(10都市) | |||||||||
| 室蘭市 | 岩見沢市 | 芦別市 | 江別市 | 苫小牧市 | 赤平市 | 千歳市 | 歌志内市 | 恵庭市 | 伊達市 |
| 北海道の10都市を見ると、特徴が浮かび上がります。芦別市、赤平市、歌志内市などはかつて隆盛を極めた炭坑都市。当時(特に。昭和30年前後)合併などは、考えられなかったのかもしれませんね。(なお、歌志内市は、人口順位で670番の最下位となっています。)また、室蘭市も以前は新日鉄室蘭があり裕福な鉄鋼都市であったことがこれにも表れている気がします。 | |||||||||
| 宮城県(1市) | |||||||||
| 多賀城市 | |||||||||
| 多賀城市は、平安時代までは、陸奥の国府が置かれた地です。近隣に仙台市、塩竈市(しおがまし)があるのにかかわらず、これらと合併せず、独自に昭和26年 7月 1日に町制施行し、昭和46年11月 1日に市制施行しました。歴史的背景として考えられるのは、昭和17年に海軍工廠(かいぐんこうしょう・旧海軍の兵器や物資を生産した工場)が設置され、終戦とともにアメリカ軍が駐留、解放後の跡地に工場を誘致して人口の増加が進んだため、他と合併しなくても単独で町制施行できたためと思われます。 | |||||||||
| 東京都(11都市) | |||||||||
| 武蔵野市 | 三鷹市 | 小金井市 | 小平市 | 東村山市 | 国分寺市 | 狛江市 | 清瀬市 | 東久留米市 | |
| 稲城市 | 多摩市 | ||||||||
| 東京都の特徴は、このパターンがかつての旧北多摩郡域に集中していることです。上記表では、武蔵野市から東久留米市までの9都市が旧北多摩郡域です。都心から近いため早い時期から人口増加に恵まれて、他の市町村と合併しなくても単独で成立できたたことが要因と思われます。(多摩市、稲城市は旧南多摩郡域)なお、西多摩郡域にはこのパターンの都市は1市もありません。 | |||||||||
| 神奈川県(1市) | |||||||||
| 綾瀬市 | |||||||||
| 綾瀬市にある厚木基地は、昭和12年の日中戦争勃発とともに軍備が拡充されました。 そのような背景として早くから発展し昭和20年に町制が施行されました。 | |||||||||
| 埼玉県(1市) | |||||||||
| 蕨市 | |||||||||
| 蕨市は、中仙道のなかでもベスト5に入る宿場町でした。この様な背景により早くからひらけ単独での町制施行、市制施行が進んだ思われます。また、蕨市は、面積が5.10平方キロメートルで、日本一面積が狭い都市で、人口密度も最も高い都市として知られています。(1平方キロメートルあたり約14,000人) 他には、成人式の発祥地として昭和21年(1946年)に蕨町青年団が主催して式が行われ、以後意義あることとして評価が高まり、昭和23年 (1948年)7月に国民の祝日として制定されました。 |
|||||||||
| 千葉県(2市) | |||||||||
| 浦安市 | 鎌ヶ谷市 | ||||||||
| 浦安市は、明治42年町制施行にするほど早くから発展したところだったようです。鎌ケ谷市は、昭和33年、町としての標準人口である8,000人を超えていたこともあり、周辺の村々との合併もなく町制が施行されました。(町制施行時の人口は1万1498人)、昭和45年3月、地方自治法の一部が改正され、それまで市となるために必要だった人口5万人以上という条件が、昭和45年3月から47年3月までの時限立法ながら都市としての要件を満たしていれば3万人以上でも市制施行が可能となり昭和46年9月1日鎌ケ谷市が誕生しました。(市制施行時の人口は4万4760人) | |||||||||
| 京都府(1市) | |||||||||
| 向日市 | |||||||||
| 福岡県(1市) | |||||||||
| 春日市 | |||||||||
| 宮崎県(1市) | |||||||||
| 小林市 | |||||||||
| 鹿児島県(1市) | |||||||||
| 串木野市 | |||||||||
| 沖縄県(4市) | |||||||||
| 宜野湾市 | 具志川市 | 浦添市 | 平良市 | ||||||
| 西日本地域の8市は、それぞれ古くから政治や経済の中心地として栄えて所が多いようです。資料が少ないため今後調査して詳細を掲載してゆきます。ご容赦下さい。 | |||||||||
| 清瀬村誕生に戻る | |||||||||
| 資料№4:全国の清瀬をさがせ | ||
| 全国にある、清瀬という地名を探しております。もし下記の表に記載されていなくて、現存する場所がありましたら、メールか掲示板にてお知らせ下さい。 | ||
| 1,郵便番号簿に記載されている清瀬という場所 | 059-3353 北海道三石郡三石町清瀬 | |
| 376-0026 群馬県桐生市清瀬町 | 2000年8月、現地調査しました。 詳細はここをクリックしてご覧下さい。 |
|
| 921-8122 石川県金沢市清瀬町 | ||
| 669-1131 兵庫県西宮市清瀬台 | ||
| 692-0035 島根県安来市清瀬町 | ||
| 744-0071 山口県下松市清瀬町 | ||
| 839-1312 福岡県浮羽郡吉井町清瀬 | ||
| 2,郵便番号に記載されていない清瀬という場所 | 新潟県新津市論瀬という近くにある、清瀬 | |
| 東京都小笠原父島にある清瀬地区 | ||
| 清瀬の地名の由来に戻る | ||
| 清瀬の四季・春へ | 清瀬の四季・夏へ | 清瀬の四季・秋へ | 清瀬の四季・冬へ |
| 思い出鉄道紀行 本館 1970年代 後半からの鉄道 |
思い出鉄道紀行 新館 2000年以降の 活躍中の鉄道 |
思い出鉄道紀行 別館 廃線跡の探訪記録 |
海外乗物紀行 海外訪問地の 鉄道・バス |
| 乗合バス紀行 バスの乗車記録 |
つばさ紀行 搭乗した 旅客便の記録 |
ケアンズ紀行 ケアンズの紹介 |
ユースホステル 紀行 YHの宿泊紀行 |
| 東日本紀行 東日本各地を紹介 |
新潟紀行 新潟県内の 市町村を紹介 |
ホームタウン清瀬 清瀬市の紹介 |
諸国物産味めぐリ 全国の銘品を紹介 |
| 催事販売班 フリマ参加記録 |
サイトマップ ホームページ の内容一覧 |
お奨めリンク集 LINK |
リンクバナーの森 |
| 店主の紹介 |
使用機材の紹介 | 掲示板へどうぞ! さばきよ商店のひろば |
トップページ へ戻ります |