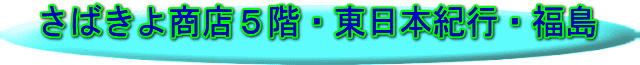
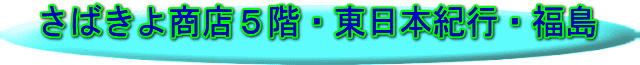
| 福島県のプロフィール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福島県のプロフィールをご紹介します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、福島県の位置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東経139度〜141度、北緯36度〜37度の間に位置し、宮城県、山形県、新潟県、茨城県、栃木県、群馬県と接しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、同緯度の都市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ギリシャ南部や、アメリカ・カリフォルニア州サンフランシスコとほぼ同緯度にあたります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、長さ・面積 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福島県の県域は、東西166km、南北133kmに広がり、総面積は13,781平方キロメートル全国の自治体の中では第3位の広さを有しています。また、人が住むことが可能な面積(可住面積)は4,127平方キロメートルで、北海道、新潟県につぎ第3位の面積を有しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、人口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人口は、213万3千人で、全国17位となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1871年 | 明治4年 | 廃藩置県が施行され、県内に11あった藩が、福島・若松・磐前の3県に集約されました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1876年 | 明治9年 | 福島・若松・磐前の3県が統一されて、現在の福島県が誕生した。なお、県庁は当時福島城のあった場所に置かれました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1887年 | 明治20年 | 東北本線(当時は日本鉄道線)が黒磯・岩切(宮城県)間が開通し上野駅と結ばれました。福島の伊達地方(福島市周辺地域)では、江戸時代の終わり頃から養蚕業が盛んに行われており、開通した鉄道を利用して大量に生糸が運ばれ輸出されました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1888年 | 明治21年 | 磐梯山が大噴火を起こし、これにより3つの集落が全滅し。461人が死亡。泥流は檜原川・長頼川をせき止め、現在の磐梯高原の大小100余の湖沼を作り出しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1894年 | 明治27年 | 常磐線(当時は日本鉄道・海岸線)の工事が開始されました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1898年 | 明治31年 | 水戸・岩沼間が開通し、浜通りの産業は大きな発展を遂げました。特に、いわき市の常磐炭田は、近代設備を導入にしたことにより、生産量が大幅に増加し、当時東京地方で使われる石炭のほとんどが常磐炭鉱のものだったと言われています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1899年 | 明治32年 | 福島の経済は急速に発展し、東北地方で初めて福島に日本銀行の支店が開設されました。(仙台市より先に開設されている点に当時の隆盛ぶりがうかがえます。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1900年 | 明治33年 | 20世紀初頭の人口は、109万人で全国16位です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1914年 | 大正3年 | 磐越西線・郡山・新津間が全通しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1917年 | 大正6年 | 磐越東線・平〜郡山間が全通しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1927年 | 昭和2年 | 福島交通、福島・飯坂温泉間が全通。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1934年 | 昭和9年 | 水郡線・水戸・安積永盛間が全通。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1957年以降 | 昭和32年 | 浜通りの中部地区に原子力発電所が次々に建設されました。なお、発電された電力は、主に首都圏に送電されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1959年 | 昭和34年 | 日本最大の貯水式田子倉発電所(田子倉ダム)が只見町に建設されました。(発電能力38万キロワット) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1971年 | 昭和46年 | 只見線会津若松・小出間全通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1973年 | 昭和48年 | 東北自動車道、白河・郡山間開通。(矢板〜白河未供用のため首都圏とは未接続) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1974年 | 昭和49年 | 東北自動車道、矢板・白河間開通。(首都圏と直結した。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1975年 | 昭和50年 | 東北自動車道、郡山・白石間開通。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982年 | 昭和57年 | 東北新幹線・大宮―盛岡間開通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987年 | 昭和62年 | 国鉄・会津線、西若松・会津滝ノ原(現在の会津高原)間、会津鉄道に転換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988年 | 昭和63年 | 阿武隈急行、福島・槻木間全通。なおこの鉄道は、JR以外では、初の交流電化の鉄道として有名です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993年 | 平成5年 | 福島空港開港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、地域の違い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福島県は東に阿武隈高地、西に奥羽山脈が南北に走り、東から浜通り、中通り、会津、に3つにわけられます。3つの地域には単に地形的な違いだけでなく、気候的、経済的、文化的な相違が見られます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地勢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜通り | 阿武隈高地の東側の地域で、太平洋沿いに約160kmの海岸線が走る低地帯となっており、西側を走る阿武隈高地で中通りと接しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中通り | 阿武隈高地と奥羽山脈に挟まれた地域で、阿武隈川が南から北に流れ郡山盆地や福島盆地を形成しています。大部分が平坦地で地味肥沃です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会津 | 新潟県境に連なる越後山脈と奥羽山脈の地域です。全般に起伏の大きな山地が占める地方で、北部一帯には磐梯山と猪苗代湖、磐梯高原、南西には尾瀬湿原と東北一高い燧ケ岳(2,356m)があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気候 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気候の面からも中通り、会津、浜通りの3つの地域に分けることができます。桜の開花は、浜通り、中通り、会津の順です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜通り | 海洋性気候のため、夏(7月から8月)は海から涼風が吹き比較的過ごしやすい気候です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中通りの平坦部 会津の盆地 |
夏は蒸し暑く、特に福島市は湿度が非常に高く全国的にも有数の厳しい暑さとなります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中通り山間部 会津の山間部 |
夏は、それほど暑くならず過ごしやすい地域です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会津の冬の様子 | 会津地方は冬に積雪が多く、特に南西部の只見地方は4mに達することもある豪雪地帯です。それに対し太平洋側の浜通りは冬でも比較的温暖で降雪日が数えるほどしかありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、県内各都市の様子(市制施行順) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 思い出鉄道紀行 本館 1970年代 後半からの鉄道 |
思い出鉄道紀行 新館 2000年以降の 活躍中の鉄道 |
思い出鉄道紀行 別館 廃線跡の探訪記録 |
海外乗物紀行 海外訪問地の 鉄道・バス |
| 乗合バス紀行 バスの乗車記録 |
つばさ紀行 搭乗した 旅客便の記録 |
ケアンズ紀行 ケアンズの紹介 |
ユースホステル 紀行 YHの宿泊紀行 |
| 東日本紀行 東日本各地を紹介 |
新潟紀行 新潟県内の 市町村を紹介 |
ホームタウン清瀬 清瀬市の紹介 |
諸国物産味めぐリ 全国の銘品を紹介 |
| 催事販売班 フリマ参加記録 |
サイトマップ ホームページ の内容一覧 |
お奨めリンク集 LINK |
リンクバナーの森 |
| 店主の紹介 |
使用機材の紹介 | 掲示板へどうぞ! さばきよ商店のひろば |
トップページ へ戻ります |