 |
戦時中、現在のひばりが丘団地付近に中島航空金属田無製造所があり、西武池袋線・東久留米駅から引き込み線がありました。今回当店相互リンク先のデトニ様にお誘い頂きこの線路跡を探訪してきました。 |
 |
戦時中、現在のひばりが丘団地付近に中島航空金属田無製造所があり、西武池袋線・東久留米駅から引き込み線がありました。今回当店相互リンク先のデトニ様にお誘い頂きこの線路跡を探訪してきました。 |
| 中島航空金属への引き込み線の概略 | ||||||
| 群馬県太田にて発祥した中島飛行機は、「優秀な人材を確保するためには東京に進出する」として機体は群馬、発動機(エンジン)は東京近郊と地域を分け事業展開をすすめました。(1938年には、本社を東京に移転) 東京近郊でのエンジン主力工場は、北多摩郡武蔵野町にあった武蔵製作所でした。中島飛行機のエンジンは、高性能として定評を得て、誉型エンジン、栄型エンジンなど生まれました。特に栄型エンジンは、三菱が開発した零式戦闘機のエンジンにも採用されていました。(歌にも歌われた、加藤隼戦闘隊の隼もこの中島飛行機が開発しました。) 昭和初期、中島飛行機の田無試運転工場(出来上がったエンジンの調整と試運転のための工場)が田無町の北部、谷戸に開設され、1938年(昭和13年)隣接地に、中島飛行機田無鋳鍛工場(じゅたんこうば)が開設されました。工場名でもわかるとおり、鋳造(ちゅうぞう・いもの)や鍛造(たんぞう)でエンジン部品を製造しておりました。なお、翌年に中島航空金属と改称しております。 鋳造(ちゅうぞう・いもの)は、砂などで作った型に、熱で溶かした金属を流し込んで作るもので大量の砂を必要とします。この中島航空金属では、当初西武池袋線・ひばりが丘駅(当時の駅名は、田無町)に着荷した砂を、駅から工場まで人が運搬していました。だんだんと人力に頼る運搬では限界に達するようになり、東久留米駅からに引き込み線が敷設されるようになりました。 引き込み線の用地は、軍か中島側で用意し線路の敷設権は西武鉄道が取得して引かれたようです。軌間(線路の幅)は、1067ミリメートルで、単線で運転されていたと思われます。なお当時の動力については、電化されていたと思われる文献がある反面、蒸気機関車が牽引していたという意見もあり判断しかねる点でもあります。なお、近在の小学5・6年生が人力で貨車を押したとの記録も残されています。 終戦後、線路自体は残り東久留米、保谷、田無にまたがる「ひばりが丘団地(1959年・昭和34年入居開始)」建設時は、資材運搬線として活用されたとの記録も残っております。なお、この中島航空金属の用地の一部が、「ひばりが丘団地」に転用されているとのことです。 現在は、東京電力の高圧線が当時の線形に近い形で通っており、一部は、散歩道になっております。なお落合川を渡る橋脚や築堤に引き込み線の痕跡が残されており当時をしのぶことができます。 (上記、解説文作成にあたり、旧・田無市史、東久留米市史などを参考にさせて頂きました。なお、上記文章に誤記、表現方法での誤まり等ございましたらぜひともご指摘、ご教示頂きますようにお願い申し上げます。) |
||||||
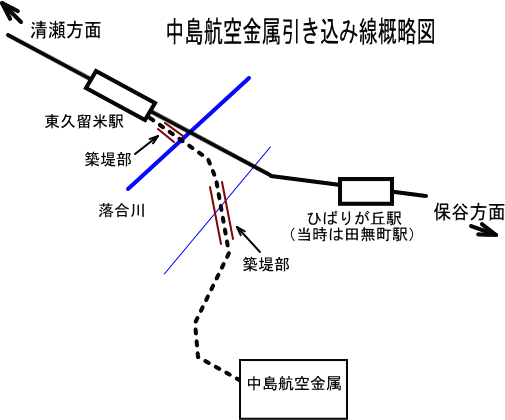 実際よりかなり簡略化して作成しています。(描画責任:さばきよ商店・デザイン室) |
||||||
| 東久留米駅付近の様子 | ||||||
 関東の駅100選にも選ばれている 西武池袋線・東久留米駅です。 この駅から旧・中島航空金属へ 引き込み線が伸びていました。 |
 東久留米駅下りホームです。(清瀬方面) 現在の下りホーム付近から工場への 引き込み線があったと思われます。 |
|||||
 下りホーム・池袋寄りです。 ホーム後方が、何となく盛り上がっております。 道床の跡かもしれませんね。 |
 東久留米駅池袋よりにある踏み切りです。 もうすぐ廃止されてしまいます。 手前を引き込み線が通っていたようです。 |
|||||
 東久留米駅を池袋方向からのぞみます。 雑草が生える手前の空き地が、かつての引込み線の跡と思われます。 |
||||||
 踏み切りの先より池袋方向を望みます。 引き込み線の線形は、次第に右に曲がっていた様です。 |
 西武鉄道の変電所を背に引込み線跡を望みます。 周囲の柵は、枕木を利用したものです。 |
|||||
 築堤の横側です。 木々の奥が築堤となります。 |
 築堤に咲く花です。 |
|||||
 落合川手前の築堤終端部です。 このあたりから、鉄橋でこの川を渡った様です。 |
 落合川手前の築堤終端部の柵です。 かつて使用していた枕木かもしれません。 |
|||||
| 落合川周辺 | ||||||
 落合川です。左岸、カンナの花の奥が築堤の終端となります。 なお、中央奥は、西武池袋線です。ちょうど2000系が橋を渡って行きます。 |
||||||
 落合川右岸から見る橋脚の痕跡です。 中央の木のところを線路が通っていました。 |
 東久留米駅からの線路は、落合川を 渡りこのあたりを通っていたと推測されます。 (中央の木は、左の写真と同じ木です。) |
|||||
 東京電力の高圧線がゆるいカーブを 描き右に進んでいます。 このあたりにも廃線跡を感じますね。 |
 西武池袋線の踏み切りです。 ちょうどNRAが通過して行きます。 普段電車から見る踏み切りも反対側から見ると新鮮に 見えます。ここが、たての録道の入口となります。 |
|||||
| たての録道 | ||||||
 たての録道の入口の看板です。 |
 たての録道が続きます。 奥に見える畑では、何を作っているのでしょうか? |
|||||
 大根でした。青々した新鮮さがいいですね。 |
||||||
 中間部にある築堤です。 このあたりは、谷地にあるため 築堤が作られた様です。 |
 中間部にある築堤の下を通る小さな川です。 このあたりは、武蔵野のハケを水源とした 川が多く流れています。水もきれいです。 |
|||||
 中間部にある築堤からの階段です。 |
||||||
 中間部にある築堤を過ぎると、切り通しとなっております。 勾配も10から15パーミル(1000メートル進むと10から15メートル上がる)程度あるようです。 |
||||||
 たての録道ももうすぐ終了する地点です。(東久留米駅方向を望むます。) |
||||||
| ひばりが丘団地付近 | ||||||
 線路は、現在鉄塔のあるところを抜け現在のひばりが丘 団地西部から左に折れ工場に向ってました。 |
 線路は、左側の木の左側を通りこのあたりから 東に進路を変え、工場に向っていました。 |
|||||
 ひばりが丘団地西部で、この付近から工場へ 線路が直進していたと思われます。 |
 住友重機械工業前のバス停です。 数度このバス路線を乗り何でこんな所に 工場があるのかなと疑問に感じていました。 それが、今回の探訪により、戦時中旧・田無町域が 多摩地区でも有数の工場地帯に発展した事が判明。 また、ここに中島航空機関連の工場があった 事も初めて知りました。清瀬から近い地域でありながら 全くその事実を知らずにおり、今後も近隣地域の調査を 着実に進めて行きたいと思いました。 |
|||||
 かつての中島航空金属は、戦後日特金属 工業となり現在は、住友重機械工業に 吸収合併されております。 |
||||||
| トップページに戻る | 思い出鉄道紀行・新館に進む | 思い出鉄道紀行・本館に進む | |||
| 思い出鉄道紀行・別館に進む |